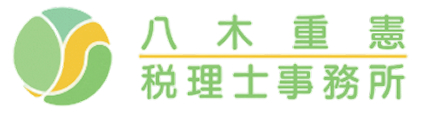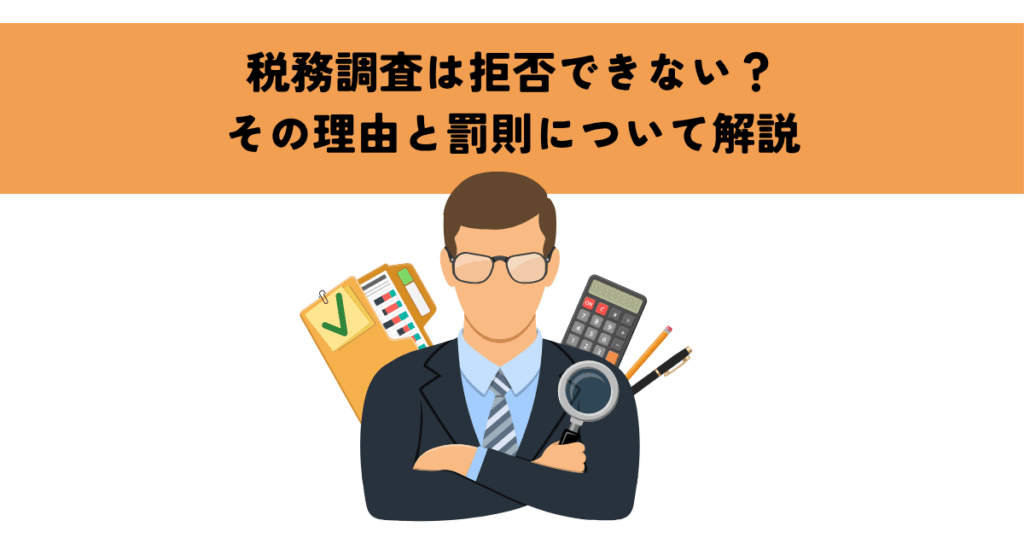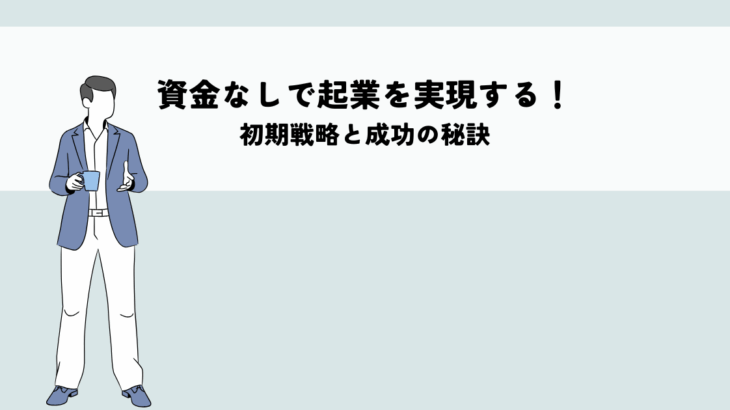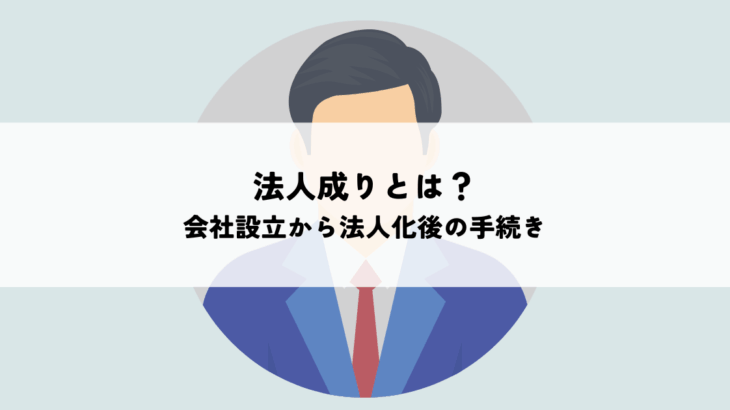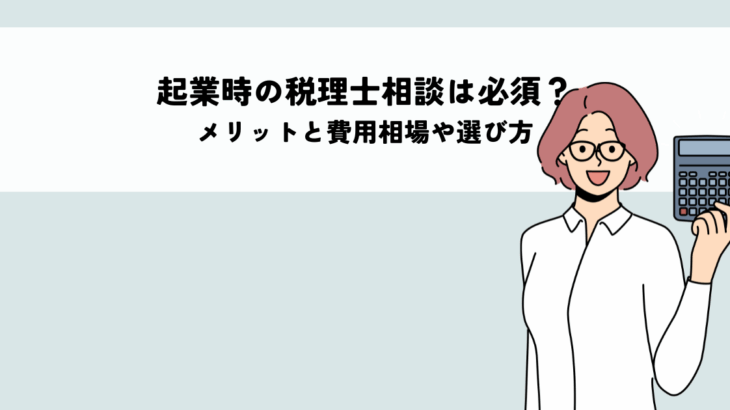ある日突然、税務署から「税務調査に伺います」という連絡がきたら、誰しも動揺するでしょう。
仕事が忙しい時期であったり、帳簿の準備が万全でなかったりすると、「いっそ拒否できないか」と考えてしまうかもしれません。
しかし、税務調査を正当な理由なく拒否することは、法律で認められていないのが現実です。
では、なぜ拒否できず、もし拒否したらどうなるのでしょうか。
今回は、税務調査を拒否した場合のリスクと、知っておくべき正しい対応方法を解説します。
税務調査は原則として拒否できない理由
法律で定められた受忍義務
納税者には、税務調査を受け入れなければならない「受忍義務」が法律で定められています。
これは、憲法で定められた「納税の義務」を適正に果たしているかを確認するために、国に与えられた重要な権限の一部です。
そのため、納税者側の都合だけで一方的に調査を拒むことはできません。
この義務があるからこそ、税務調査は原則として断れないのです。
調査官が持つ「質問検査権」
税務署の調査官は、法律に基づいて納税者やその関係者に対して質問を行ったり、帳簿書類などの関係物件を検査したりする「質問検査権」という権限を持っています。
この権限は非常に強力で、調査官は業務に関するあらゆる資料の提示を求めることができます。
受忍義務とこの質問検査権があるため、税務調査は任意とされつつも、実質的には強制力を持っているのです。
任意調査と強制調査の違い
一般的な税務調査は、事前に納税者の同意を得て行われる「任意調査」です。
しかし、これまで説明した通り、受忍義務があるため実質的に拒否はできません。
一方で、脱税額が大きく悪質であると判断された場合には、裁判所の令状を持って強制的に行われる「強制調査」に切り替わることもあります。
これは国税局査察部、通称「マルサ」が行うもので、一切の拒否は認められません。

税務調査の拒否で科される罰則
懲役または罰金が科される可能性
もし正当な理由なく税務調査を拒んだり、調査官の質問に対して黙秘したり、嘘の回答をしたりした場合には、明確な罰則が定められています。
国税通則法により、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
安易な拒否が、思わぬ刑事罰につながるリスクがあることを知っておくべきです。
追徴課税や加算税のリスク増大
調査への非協力的な態度は、金銭的なペナルティを増大させることにも繋がります。
調査を拒否し続けると、税務署は限られた情報から税額を推定して課税する「推計課税」を行うことがあります。
その結果、本来納めるべき税額よりも多額の納税額を請求される恐れがあるのです。
さらに、意図的に帳簿を隠していると判断されれば、最も重いペナルティである「重加算税」が課される可能性も高まります。
税務署からの心証が悪化するデメリット
目に見える罰則以上に厄介なのが、税務署からの心証が悪化することです。
一度「非協力的な納税者」というレッテルを貼られてしまうと、その後の調査がより厳格かつ詳細に行われるようになる可能性があります。
また、将来的に税務調査の対象として選ばれやすくなるなど、長期的に見て大きなデメリットを被ることになりかねません。
税務調査で拒否以外にできる対応
正当な理由がある場合の日程変更
いきなり調査を拒否するのではなく、まずは日程の変更が可能か相談することが現実的な第一歩です。
例えば、病気や入院、身内の不幸といったやむを得ない事情や、どうしても外せない取引があるなどの業務上の都合は、日程変更の「正当な理由」として認められる場合があります。
正直に状況を伝え、誠実な姿勢で交渉することが重要です。
税理士への速やかな相談
税務調査の連絡が来たら、自分一人で抱え込まず、すぐに税務の専門家である税理士に相談してください。
税理士は、税務調査がどのような流れで進むのか、何を準備すべきか、どのような点に注意すべきかを熟知しています。
専門家からの客観的なアドバイスは、不安を和らげ、適切な初動対応を可能にしてくれます。
調査の立ち会いを税理士に依頼する
税理士は、調査当日に納税者の代理人として立ち会うことができます。
これは非常に心強い選択肢です。
調査官との専門的な質疑応答や交渉を全て任せることができ、納税者本人は事業の説明に集中できます。
不当な指摘や高圧的な態度に対しても、税理士が防波堤となってくれるため、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。
調査当日の受け答えに関する注意点
調査当日は、調査官の質問に対して誠実に対応する姿勢が基本です。
ただし、聞かれたこと以上に余計な情報を話す必要はありません。
もし質問の意図が分からなかったり、すぐに回答できない内容であったりした場合は、曖昧に答えず、「確認して後日回答します」と明確に伝えることが大切です。
冷静かつ的確な受け答えを心がけましょう。
まとめ
税務調査には受忍義務があり、正当な理由なく拒否すると罰則が科されるリスクがあります。
拒否という選択は、追徴課税の増大や税務署からの心証悪化など、多くのデメリットにつながりかねません。
調査の連絡を受けたら、まずは慌てずに日程変更が可能か検討し、速やかに税理士に相談しましょう。
専門家のサポートを受けながら誠実に対応することが、調査を円滑に進め、自らを守るための最善の方法です。